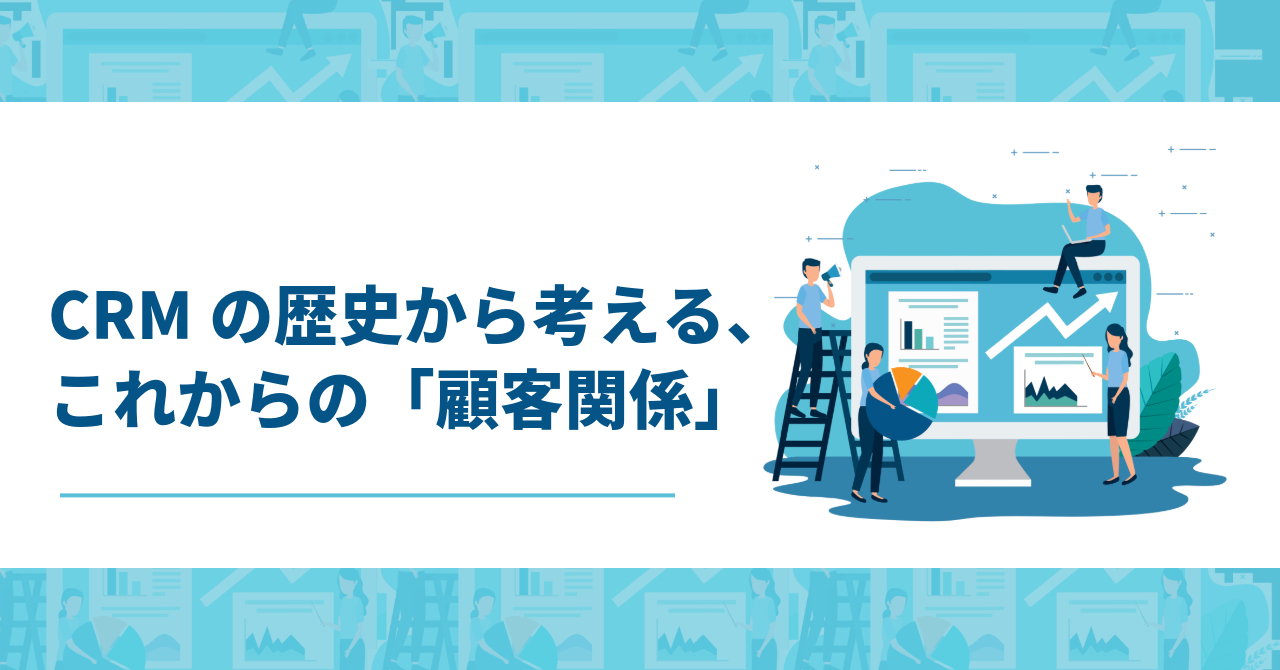「CRM」と聞いて「顧客管理のツール」と思い受かべる方も多いかもしれません。
しかしその背景には、時代とともに進化してきた“顧客との関係づくり”の考え方があります。
本コラムでは、CRMの歴史や技術の進化をふまえながら、これからの時代に求められる顧客戦略や、CRMツール選びの視点について考察します。
CRMとは何か?

CRMとは「Customer Relationship Management(顧客関係管理)」の略で、企業と顧客の関係性をより良いものにするための考え方や仕組みを指します。多くの場合は「顧客管理システム」や「営業支援ツール」として知られていますが、その本質は単なる情報の蓄積や管理にとどまりません。
CRMの基本的な定義や機能について詳しく知りたい方は、こちらの「CRMとは?」の記事もあわせてご覧ください。
近年では、CRMは“関係性の設計図”ともいえる役割を担っています。企業がどのように顧客と関わり、どのタイミングでどのような価値を提供するのか。その全体像を描き、実行を支えるのがCRMの要な役割のひとつです。

CRM(顧客管理)とSFA(営業支援)の違いとは?

時代とともに変化してきたCRMの役割と顧客戦略
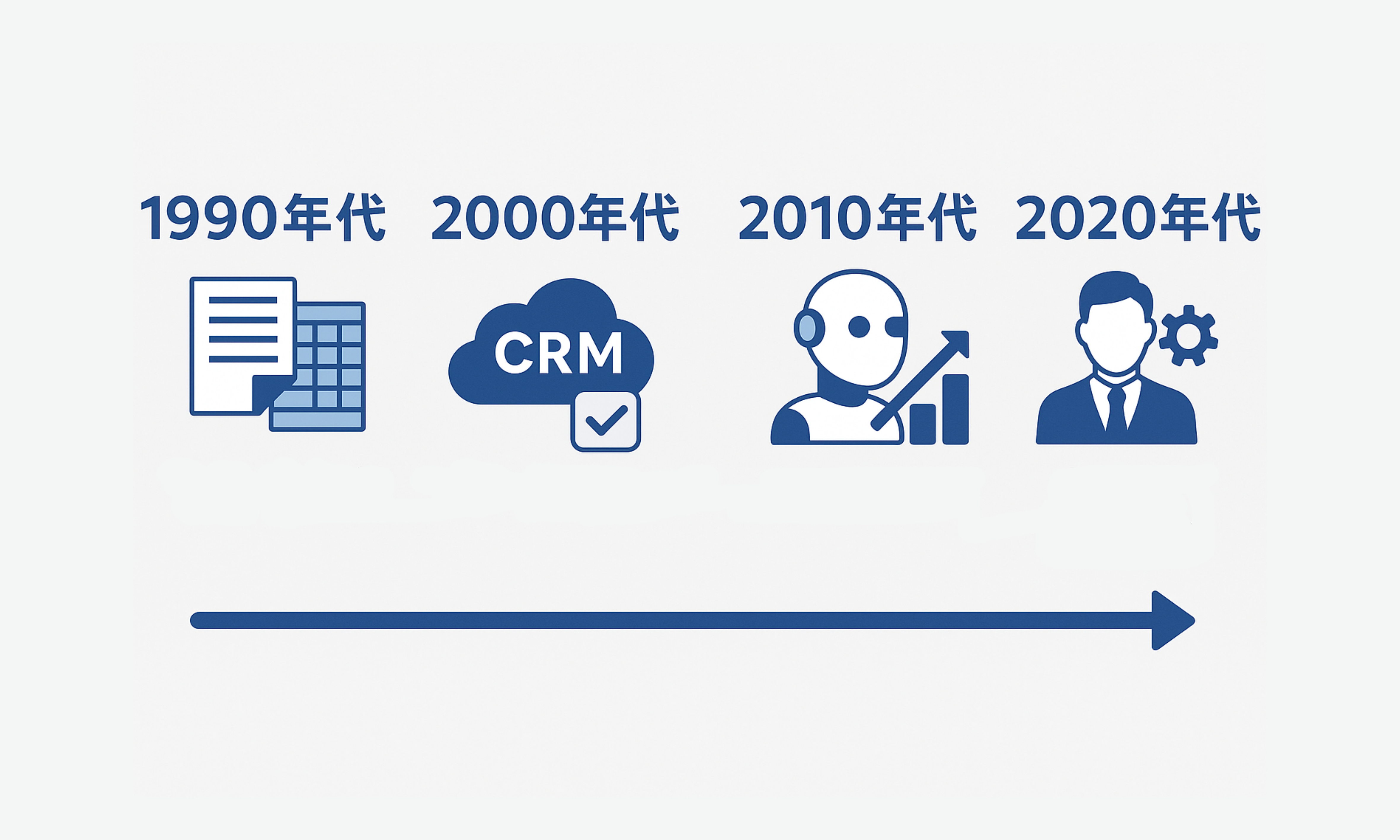
CRMは、もともと顧客情報を管理するためのシステムとして使われてきましたが、テクノロジーの進化や働き方の変化とともに、その役割も広がり続けてきました。今では、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、企業全体で顧客との関係を支える“基盤”として活用されています。
このように、CRMの変化は企業と顧客の関係のあり方そのものを映し出しています。
では、これからの時代、私たちはどのように顧客との関係を捉えていくべきなのでしょうか?
そのヒントを探るために、CRMの進化をたどりながら、時代ごとの背景と役割の変化を振り返っていきましょう。
1990年代、理想としての「顧客一元管理」
1990年代、CRMは「顧客の情報を一元的に管理し、最適な対応を実現する」という理想のもとに登場しました。
当時は主に大企業がオンプレミス型のCRMを導入し、営業・マーケティング・カスタマーサービスといった部門間で顧客情報を共有しようとする試みが見られました。
しかし実際には、導入コストの高さや社内システムの複雑さ、部門ごとの運用ルールの違いなどにより、理想通りに活用できないケースも多く存在しました。
それでもこの時代に広がった「顧客中心」の発想は、まぎれもなくCRMの進化の出発点となりました。
2000年代、クラウド化による柔軟な運用と普及の兆し
2000年代に入ると、CRMは大きな転機を迎えます。
Salesforceをはじめとするクラウド型CRM(SaaS型)の登場により、従来のような高額な初期投資や複雑なシステム構築が不要になり、より柔軟で迅速な導入が可能になりました。
日本国内でも2000年代後半から、こうしたクラウドCRMが徐々に注目されるようになります。とくに外資系企業やIT系の中堅企業といった、変化への感度が高い企業を中心にさいようが進みました。
グローバル本社がSalesforceを導入していた影響や、社内に十分なIT開発リソースがない事情から手軽に導入できるクラウド型を選択する傾向がありました。
当時はクラウド活用の基盤や、セキュリティ意識もほとんど整っておらず、導入事例は限定的でしたが、インフラの整備やスマートデバイスの普及により、徐々に利用ハードルが下がり、中堅企業層へ拡がっていきます。
CRMはこの時期から「導入が難しいシステム」から「手の届く実用的なツール」へと変化を始めました。
2010年代、AIとMAによる“CRMの頭脳化”
2010年代には、CRMは情報の記録・共有にとどまらず「判断」や「アクション」を支援するツールへと進化していきます。
マーケティングオートメーション(MA)やAI(人工知能)との連携が進み、顧客データを活用した営業活動の最適化や、キャンペーンの自動化、購入傾向の分析などが可能になりました。
こうした高度な機能により、CRMは現場の判断力を支える“頭脳”にような存在となり、営業部門だけでなくマーケティングや経営層の意思決定にも貢献するようになります。
これらの機能はもともと欧米で発展しましたが、2010年代の後半から日本国内でも大手企業を中心にMAやAIを活用したCRM運用が徐々に広がりはじめました。
特にBtoB領域では、リード獲得から商談管理までを一貫して自動化・可視化するニーズが高まり、CRMが営業支援システムから統合顧客プラットフォームへ進化する流れが生まれます。
また、スマートフォンやクラウドサービスの普及により「どこからでもアクセスできるCRM」が当たり前になり、企業の業務スタイルやチームの連携方法そのものを変えていきました。
2020年代、自律性と現場主導の時代へ
2020年代に入り、CRMの特徴として特に注目されるのが「自律性」と「現場主導性」です。ノーコード・ローコードの進化により、ITの知識がなくても、現場の担当者が自ら業務に合わせて項目や画面をカスタマイズできるようになりました。
日本国内でも、コロナ禍を契機にクラウドシフトが加速し、SaaS型CRMを現場主導で柔軟に活用する動きが広がっています。
業種特化型のCRMやkintoneのような国産のノーコード型ツールも台頭し、「IT部門主導ではなく、現場の課題に合わせて“育てるCRM”」という使い方が一般化しつつあります。
また、生成AIの活用が進んだことで、CRMは単なるデータベースではなく、提案・予測・自動対応まで可能にする“自走するツール”への期待も高まっています。
加えて、リモートワークの定着により、社内外の顧客接点を一元化・可視化する重要性が増しています。CRMは今や特定部門の専用ツールではなく、企業全体の顧客関係インフラとして、組織を横断した活用が求められる時代になっているのです。
自社に合ったCRMをどう考えるか?
これまでCRMの進化を見てきたように、その役割は「顧客情報の管理ツール」から「顧客関係を支える企業基盤」へと大きく変化してきました。
では、自社にとって本当に活用できるCRMとは、どんなものなのでしょうか?
CRMを選ぶ際に押さえておきたい3つの視点を紹介します。
自社の業務プロセスやチーム構成にフィットするか?
どれだけ高機能なCRMでも、現場の業務にフィットしていなければ活用は定着しません。営業やマーケティングだけでなく、カスタマーサポートや管理部門など、自社の業務フローや組織構成に合った形で使えるかどうかがポイントです。
ノーコード対応や柔軟なカスタマイズ性があれば、現場に合わせて使いやすく育てていくことも可能です。
部門をまたいで使える拡張性はあるか?
CRMは部門ごとに導入されるケースもありますが、全社で顧客情報を共有・活用できる環境を整えることで、より一貫した顧客対応や部門連携が実現できます。
マーケティング・営業・サポートといった部門をまたいで情報を連携できる構成かどうかは、CRMを長く活用していくうえで重要な視点です。
組織の成長や業務の変化にも対応できるCRMであれば、長期的に“使い続けられる”仕組みを築きやすくなります。
“続けられる”CRMであるか?
導入して終わりではなく、現場で使い続けられてこそ意味があります。
どれだけ高機能なツールであっても、使いづらかったり運用負荷が高かったりすれば、定着は難しくなります。
UIのわかりやすさ、業務変更の柔軟性、サポート体制の有無など「使い続けやすさ」は選定時の重要な観点です。一時的に無理をして使い続けるCRMではなく、日々の業務に自然と溶け込み現場で無理なく活用されるCRMこそが、長く成果を生みだすツールと言えるでしょう。
関連記事:失敗しないCRMツールの選び方|導入前に押さえるべき4つのポイント
顧客関係の「これから」を見据えたCRM選びを
クラウド、SaaS、AI、ノーコードとCRMを取り巻く技術は、ここ数十年で大きく進化してきました。
それにともない、CRMの役割も「顧客情報を管理するツール」から、「組織全体で顧客との関係を築くための基盤」へと広がっています。
一方で、CRMの本質的な目的は今も昔も変わりません。
それは顧客との信頼関係を構築・維持し、継続的な価値を提供することです。
しかし近年、CRMの機能が高度化したことで「何ができるか」にばかり注目が集まり、「なぜ使うのか」という本来の目的が失われるケースも少なくありません。
CRMはあくまで、顧客との関係性をより良くするための“手段”です。だからこそ、自社にとって本当に必要なのは何か?という視点で、以下のようなポイントを重視して選定しましょう。
- 自社の業務やチーム構成に合っているか?
- 部門をまたいで顧客情報を活用できる構造になっているか?
- “無理なく使い続けられる”仕組みとして運用できるか?
テクノロジーが進化しても、「誰とどう関係を築くか」は常に企業の本質的なテーマです。CRMをツールとして選ぶ前に、自社が築きたい顧客関係あり方から考えること。それこそが、CRMを「成果につながる仕組み」として活かす第一歩ではないでしょうか、
![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)