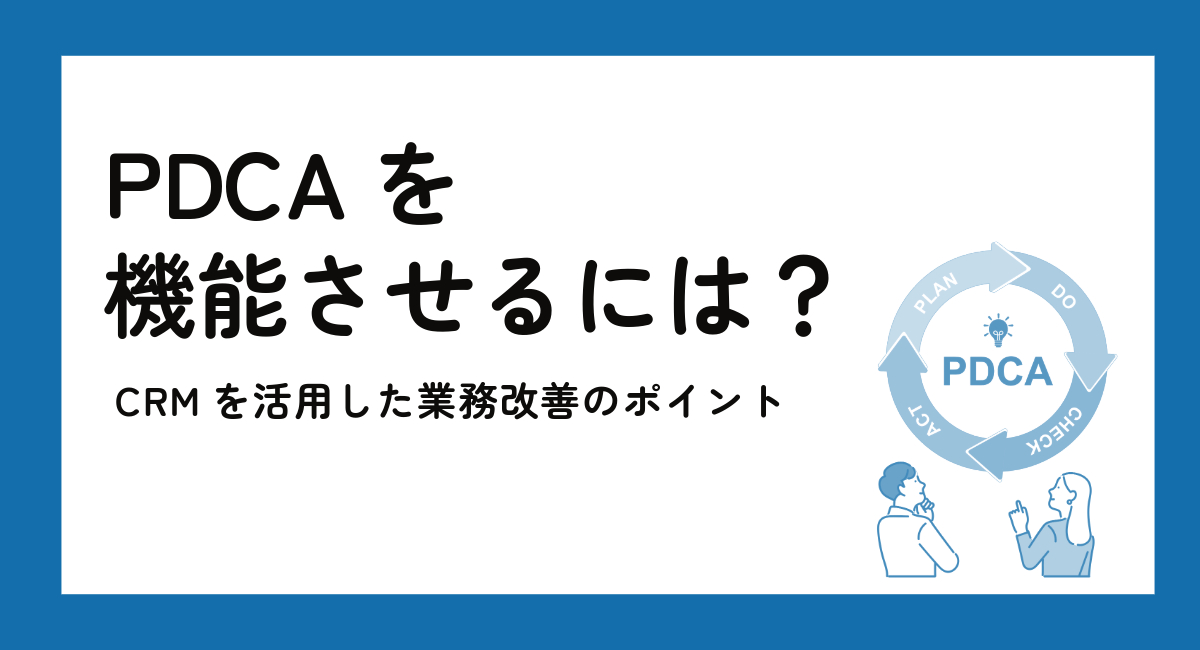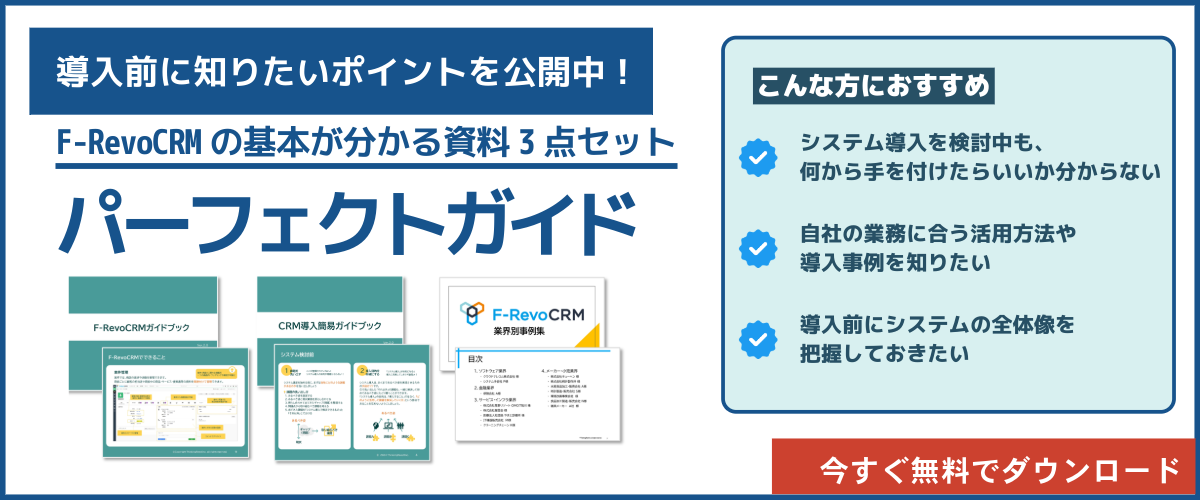PDCAサイクルは業務改善の基本として多くの企業で取り入れられています。しかし、実際には「計画を立てても行動が続かない」「振り返っても改善につながらない」といった課題が少なくありません。
その背景には、PDCAを支える仕組みが整っていないことがあります。
本記事ではCRMを活用してPDCAを定着させる方法を紹介します。
PDCAサイクルとは?

PDCAとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4つのステップで業務を継続的に改善する仕組みです。計画を立て、実行し、結果を評価して改善する。この流れを繰り返すことで業務の精度を高めていきます。
では、それぞれのステップについて具体的に見ていきましょう。
Plan(計画)
改善したい業務の目標を設定し、課題を明確にします。
具体的な数値目標を立て、「どのように進めるか」を計画します。
たとえば「今期の売上を10%向上させる」といった明確な目標を設定し、その達成に向けて必要な課題を洗い出します。
Do(実行)
立てた計画に基づいて実際に業務を進めます。
この段階では、計画通りに進めること、実施内容を記録することが重要です。
営業活動であれば、新しいアプローチの導入や顧客フォローの強化などが該当します。
Check(評価)
実行した施策が目標に対してどの程度の成果を上げたのかを振り返ります。
「どの部分がうまくいったのか」「どこに課題が残ったのか」を分析し、売上の推移や顧客満足度など具体的な数値で評価します。
Action(改善)
評価の結果をもとに、改善すべき点を修正し、次の計画へつなげます。
このサイクルを繰り返すことで、業務プロセスが継続的に向上していきます。
PDCAがうまく回らない理由と対策
PDCAを取り入れていても、「計画は立てたけれど実行が続かない」「振り返りの時間がなく改善が進まない」と感じる方は多いのではないでしょうか。
とくに営業企画部門などでは、日々の業務に追われてPDCAの各ステップを丁寧に回す余裕がなくなりがちです。
さらに部門間の情報共有が不足すると、評価(Check)や改善(Action)の精度が下がり、「同じ課題を繰り返す」結果にもつながります。
ここでは、PDCAがうまく回らない主な原因と、その解決策を見ていきましょう。
計画倒れになる【目標が曖昧】
PDCAを回そうとしても、最初の「Plan(計画)」が曖昧だと、その後の行動が具体化しません。
「売上を伸ばす」「顧客満足度を高める」といった抽象的なゴールでは、現場レベルで“何をすればいいのか”が見えにくくなります。
目標設定にはSMARTの原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)を取り入れましょう。
たとえば「3か月でリピート率を20%向上させる」といった形で、数値と期限を明確化することで、計画が行動に直結します。
実行が続かない【属人化と情報共有不足】
計画を立てても、実行が続かないケースは少なくありません。
「担当者任せで進め方がバラバラ」「報告や入力作業が負担」といった問題が積み重なると、PDCAの“Do”が形骸化してしまいます。
CRMツールを活用してタスクを可視化し、履歴を自動共有できる仕組みを整えましょう。
業務が属人化しにくくなり、チーム全体での継続的な実行がしやすくなります。
評価できない【記録が不十分でCheckが主観的】
次の課題は「Check(評価)」の精度です。
データを十分に蓄積されていないと、評価が感覚的・主観的になりがち。
「うまくいった気がする」「手応えがない」といった曖昧な判断では、改善につながりません。
KPIを設定し、ダッシュボードで成果をリアルタイムに可視化できる環境を整えましょう。
数値に基づいた客観的な評価により、次のアクションが明確になります。
改善が定着しない【Actionが単発で終わる】
改善策を出しても、そのまま「やりっぱなし」で終わってしまうケースも多く見られます。
これはPDCAサイクルが一巡で止まってしまう典型的なパターンです。
改善タスクをCRMで一元管理し、定例会議や週次レビューで次の計画に反映します。
「改善→計画」への橋渡しを仕組みとして習慣化することで、PDCAを継続的に循環させることができます。
Plan(計画)を機能させるSMARTの5原則

Plan(計画)を形だけで終わらせないためには、SMARTの5原則に沿って目標を設計することが欠かせません。
SMARTとは、具体性・測定可能性・達成可能性・関連性・期限の5つの視点で目標を設計するフレームワークです。
これらを意識することで、曖昧な理想ではなく実行につながる計画を立てることができます。
- Specific(具体的):「顧客対応スピードを上げる」ではなく、「初回応答SLAを24時間以内に短縮」といった具体的な表現にする。
- Measurable(測定可能):結果を数値で追える指標を設定し、成果を可視化する。
- Achievable(達成可能):現実的な範囲で無理のない計画にすることで、実行の持続性を確保する。
- Relevant(関連性):会社や部門の目標と整合性を持たせ、全体の方向性をそろえる。
- Time-bound(期限付き):期限を明確にし、実行責任を明らかにする。
SMARTな目標設定は、単なる数値目標の管理ではなく、「どの情報を集め、どう活かすか」を決める出発点です。
この段階で指標を明確にしておくことで、実行や評価で必要なデータが自然に集まり、PDCAを数値と事実に基づいて回すことができます。
CRMを活用したPDCAの実践方法
PDCAを継続的に回すためには、「記録」「共有」「分析」「改善」を一つの流れとしてつなぐ仕組みが欠かせません。
CRMを活用すれば、Plan(計画)からAction(改善)までをデータで一元管理し、サイクルを止めずに回し続けることができます。
CRMとは?顧客関係管理の基本・メリット・支援サービスまで徹底解説

Plan(計画)
CRMデータを分析し、最適な施策を計画。CRMに蓄積された過去のデータを分析し、売上向上のための戦略を立案します。たとえば、「過去3カ月の成約率が高い顧客層にフォーカスしたアプローチを強化する」といった計画を立てます。
Do(実行)
CRMでタスク管理し、業務を効率化。CRMを活用することで、営業担当者だけでなく、さまざまな部署で業務の効率化が実現できます。
【営業部門の場合】
CRM上でタスク管理を行い、次にやるべきアクションが明確になります。これにより、顧客対応の抜け漏れを防ぎ、より的確なタイミングでアプローチが可能になります。さらに、顧客ごとの履歴やニーズが一元管理されているため、状況に応じた最適な提案を行えます。
【カスタマーサポート部門】
CRMに記録された問い合わせ履歴をもとに、顧客ごとに適したサポートを提供できます。過去の対応内容を即座に把握できるため、迅速かつ的確な対応が可能になり、顧客満足度の向上につながります。
このように、CRMを活用することで、各部署の業務を最適化し、PDCAの「実行(Do)」をより確実に進めることができます。
Check(評価)
CRMのレポート機能を活用し、データ分析。CRMのダッシュボードを活用すると、営業活動の進捗や成約率の変化をリアルタイムで確認できます。
たとえば、「今月の商談件数は目標の80%に達しているが、成約率が低下している」といった状況をすぐに把握できるため、どこに課題があるのかを素早く分析できます。そのため、「フォローが不足している顧客に追加提案をする」「成約率が高いセグメントにターゲットを集中する」といった的確な判断が可能になり、計画通りに進んでいるかをタイムリーにチェックできます。
Action(改善)
分析結果を基に、改善策を策定。評価結果をもとに、アプローチ方法やターゲットを見直します。
たとえば、「過去のデータを分析すると、A社のような業界ではメールより電話の方がより反応率が高い」と分かった場合、同じ業界の顧客には電話フォローを強化する、といった戦略の調整が可能になります。逆に、効果が薄かった施策については、ターゲットの見直しやアプローチ方法の改善を行い、成果につながる施策へと最適化していきます。
こうした流れで、CRMを活用すれば、顧客情報や営業データを一元管理し、PDCAサイクルをよりスムーズに回せるようになります。感覚や経験に頼るのではなく、データに基づいた改善ができるため、より確実に成果を高める仕組みを構築できます。
日本食研におけるPDCA活用事例
ここまで見てきたように、CRMを活用することでPDCAサイクルを実践的に運用し、改善を仕組みとして定着させることが可能です。
では、実際にこの考え方を取り入れて成果を上げている企業の例を見てみましょう。
日本食研ホールディングス株式会社では、「販売数」よりもリピート率を重視した営業スタイルへの転換を進めました。
その実現に向けて、F-RevoCRMを活用し、営業活動における行動・商談プロセスの可視化を実施。
計画(Plan)から改善(Action)までのサイクルをシステム上で回せる仕組みを構築しました。
この取り組みにより、営業活動の標準化やモバイル活用による業務効率の向上を実現。
さらに、部門を越えた情報共有が促進され、全国の営業担当者がデータに基づく改善サイクルを自律的に回せる環境が整いました。
このように、CRMを基盤にPDCAを運用することで、現場レベルから改善が定着する仕組みをつくることができます。
PDCAサイクルを活用した業務改善:日本食研の事例
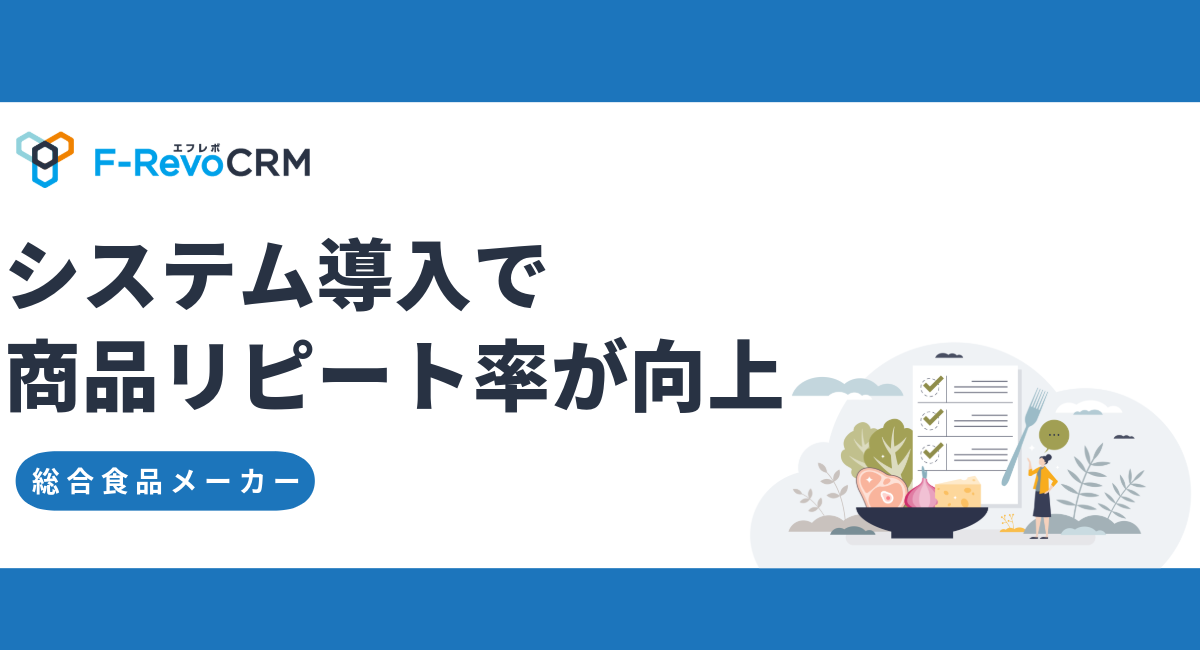
OODAとは?PDCAとの違いと使い分け
OODA(ウーダ)とは、「観察(Observe)」「判断(Orient)」「決定(Decide)」「行動(Act)」の流れで、状況に応じて素早く意思決定を行うフレームワークです。
環境変化が激しい場面では、短いサイクルで回すOODAが効果的です。
一方、PDCAは「計画 → 実行 → 評価 → 改善」を順に進め、業務の標準化や品質向上を目指す仕組みです。
つまり、OODAはスピード重視、PDCAは継続的な改善重視の手法といえます。
CRMを活用する場合、日常業務の改善やプロセス管理にはPDCAが適していますが、変化に即応する意思決定にはOODAの考え方を取り入れるとより柔軟に対応できます。
状況に応じてOODAとPDCAを使い分けることで、変化対応力と継続的な改善力の両立が可能になります。
CRMによるPDCA定着のポイント
PDCAがうまく回らない原因は、多くの場合、担当者の意識やスキルではなく、仕組みそのものが整っていないことにあります。
CRMを活用すれば、Plan(計画)からAction(改善)までの一連の流れをデータでつなぎ、サイクルを止めずに継続させることが可能です。
重要なのは、CRMを単なる顧客管理ツールとして使うのではなく、「改善を仕組み化するための基盤」として運用することです。
自社の課題を整理し、目的に合わせてCRMの設定や運用ルールを見直すことで、改善が自然と定着する環境をつくることができます。
![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)