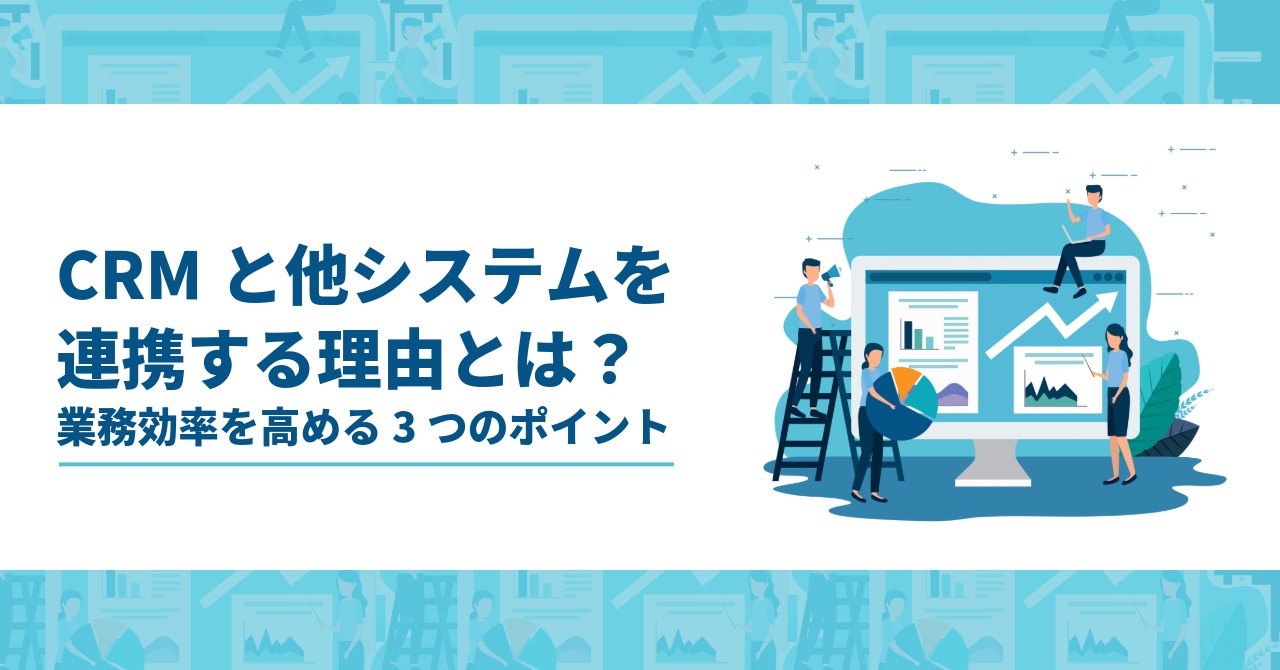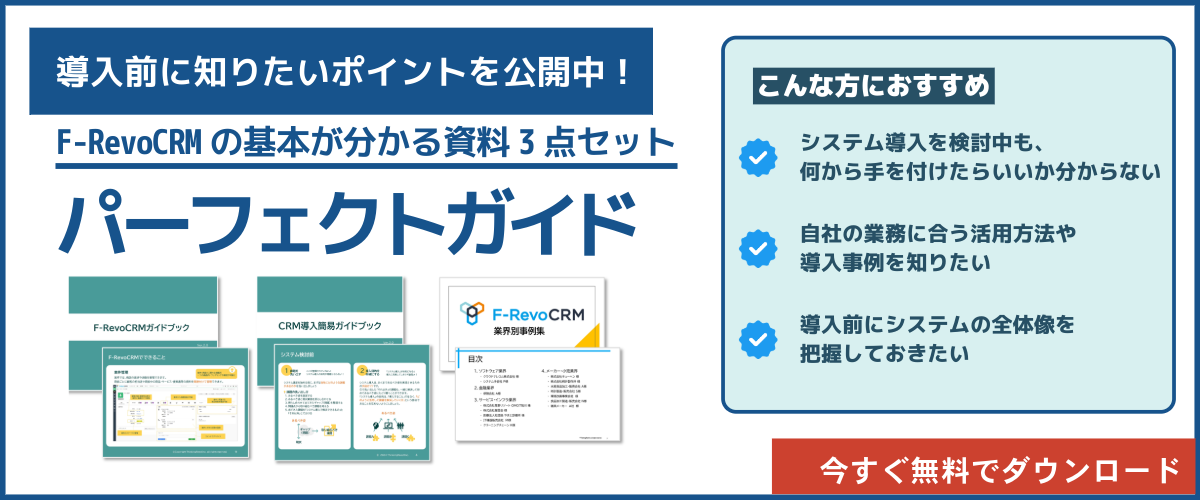顧客との関係を長期的に築くためには、情報を一元的に管理し、社内で共有する仕組みが欠かせません。
その実現を支えるのが、CRM(顧客関係管理ツール)です。
しかし、CRMを導入しても、サポートや会計などの業務システムがそれぞれ独立していると、情報が分断されてしまい、せっかく蓄積したデータを十分に活用できません。
そこで、CRMと社内の業務システムを連携することで、入力の手間を削減し、部門をまたいだ情報共有を円滑に進めることが可能になります。
本記事では、CRMと他システムを連携することで得られる3つの効果と、連携を前提としたCRM活用の考え方を紹介します。
CRMとは?顧客関係管理の基本・メリット・支援サービスまで徹底解説

CRMを導入しても「活用が進まない」原因とは?
CRMを導入すると、顧客情報を整理しやすくなり、社内での共有も進めやすくなります。
ただし、実際の業務では、顧客に関する情報が営業・サポート・会計など、さまざまなシステムに分かれて存在しているのが現状です。
そのため、CRMだけで顧客対応の全体像を把握するのは難しい場合があります。 こうしたデータを、CRMを中心につなげて活用することで、取引からサポート、請求までを一つの流れとして管理できるようになります。
これが、CRMを“他システムとの連携”を前提に考えるべき理由です。
業務システムが分断されることで起きる課題
CRMを中心に情報を連携させることの重要性を理解するには、まず業務システムが分断されたまま運用されている現状を見直す必要があります。
実際、多くの企業では営業・サポート・会計などのシステムがそれぞれ独立して稼働しています。
この状態では、同じ顧客に関する情報が複数の場所に重複して登録され、整合性を保つことが難しくなります。
たとえば、営業部が更新した取引情報が経理システムに反映されてなかったり、サポート部門が把握しているクレーム内容が営業に共有されていなかったりするケースが見られます。 こうした情報の分断は、対応の遅れや認識のずれを招き、結果的に顧客満足度の低下につながる要因になります。
CRM単体運用では業務全体をカバーできない
このように部門ごとにシステムが独立している環境では、たとえCRMを導入しても、顧客対応の全体像を把握するのは容易ではありません。
CRMは顧客情報を整理し、営業活動を効率化するうえで有効な仕組みです。
しかし、実際の業務には見積の作成、請求処理、アフターサポートなど、CRMの範囲を超えて進むプロセスが多く存在します。
そのため、CRMを単体で運用していると、情報が再び分断され、「導入したのに業務が思うように変わらない」と感じるケースも少なくありません。
CRMの価値を最大限に引き出すには、顧客対応を支える業務全体を見据え、他のシステムと連携させる前提で設計することが重要です。
連携を前提とした運用によってはじめて、CRMは組織全体の情報基盤として機能します。
CRM連携によって得られる3つの効果
では、実際にCRMを他の業務システムとつなぐと、どのような変化が生まれるのでしょうか。
ここからは、CRM連携によって期待できる3つの効果を紹介します。
①二重入力をなくし、業務負担を減らせる
多くの企業では、営業担当がCRMに登録した情報を、販売管理や会計システムにも重ねて入力しています。
この「二重入力」は単なる手間ではなく、時間と精度を損なう大きなロスにつながります。担当者は入力作業に追われることなく、顧客対応や分析など“価値を生む業務”に時間を使えるようになります。
また、手入力の回数が減ることでミスも少なくなり、業務全体の品質を安定させる効果もあります。
② 情報を一元化し、チーム間の連携をスムーズになる
部署ごとにツールが分かれていると、顧客情報を探すのに時間がかかります。
「この顧客、今どんな状況?」「最新の契約情報はどこ?」といった確認が頻発し、対応のスピードが落ちがちです。
CRMを中心に据えて他システムと連携すれば、各部門が同じ情報をリアルタイムで共有できます。たとえば、サポート部門が顧客のトラブルを把握していれば、営業は次の商談で適切な提案やフォローが可能です。
部門間の“認識のズレ”が減り、顧客対応の一貫性と信頼性が高まります。
③ データを活用し、判断や改善の精度を高める
CRMと他システムを連携させることで、取引情報やサポート履歴、請求データなどが一元的に蓄積されます。
これらのデータを分析することで、どの顧客にどのような提案が有効か、どのプロセスに改善の余地があるかといった判断がしやすくなります。
たとえば、サポート履歴から製品ごとの問い合わせ傾向を把握すれば、営業は次回の提案内容や重点を調整できます。
また、請求や入金データと照合することで、取引先ごとの売上管理や回収リスクを可視化することも可能です。
このように、システム連携は単に情報を共有するだけでなく、データを経営判断や現場の改善に活かすための基盤をつくる効果をもたらします。
代表的な連携システムと活用イメージ
CRM連携の効果を生かすためには、どの業務システムとどのようにデータをつなぐかが重要なポイントになります。
これまで見てきたような業務効率化や情報共有、データ活用の効果は、システム間の連携設計によって初めて実現します。
ここからは、代表的な連携システムと、その活用イメージを紹介します。
販売管理・会計システム ― データ入力の重複をなくす
営業が受注情報をCRMに登録したあと、販売管理や会計システムにも同じ内容を再入力しているケースは少なくありません。
この「二重入力」は入力ミスや更新漏れの原因となり、作業負担を増やします。
CRMと販売管理・会計システムを連携させることで、CRM側の登録内容が自動的に他システムへ反映されます。
見積から受注、請求までの流れが一元化され、入力漏れや金額ミスが減少します。
さらに売上データがCRMに集約されることで、営業活動の分析や売上予測にも活用できるようになります。
サポート・CTIシステム ― 顧客対応をリアルタイムに共有
顧客からの電話や問い合わせ履歴がサポートツールのみに蓄積されている場合、営業側がトラブル状況を把握できないことがあります。
CRMとCTI(電話対応システム)を連携すれば、入電時に顧客情報や過去の対応履歴を自動で表示できます。
営業は「最近の対応状況」や「未解決の案件」を確認したうえで商談に臨むことができ、サポート担当も営業活動の内容を参照しながら、対応方針を共有できます。
CTI連携でコールセンター業務を効率化したケース
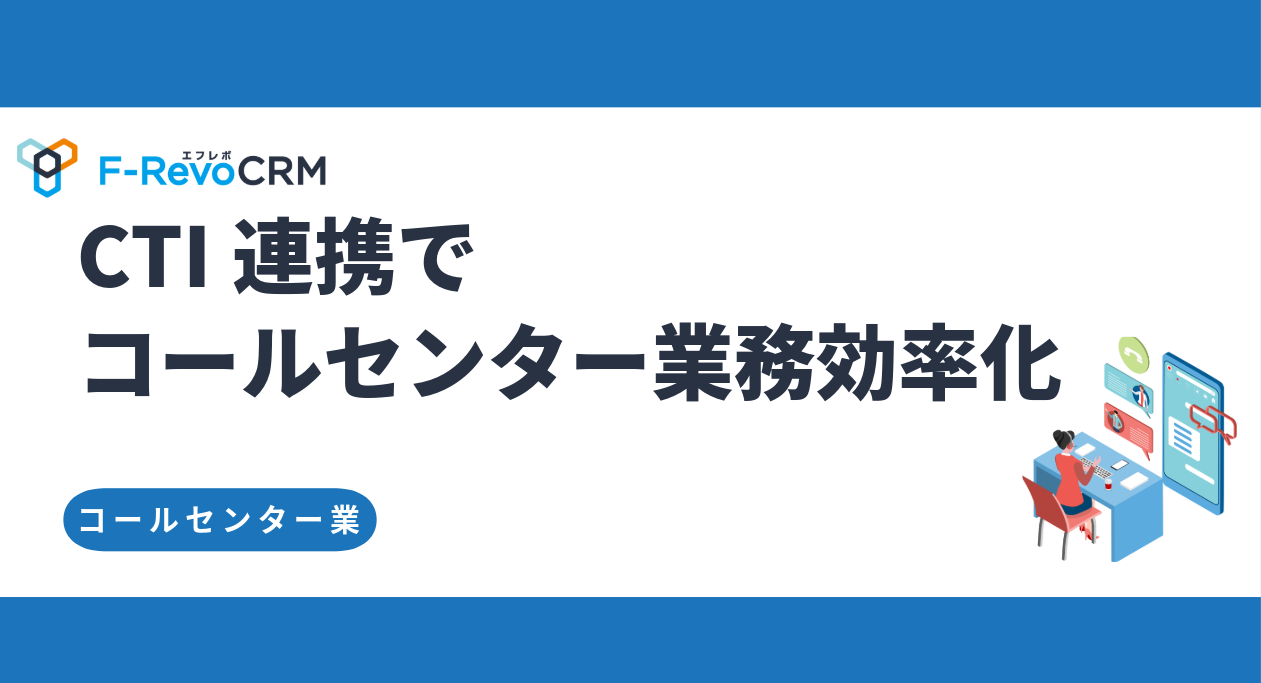
マーケティングツール(MA) ― 顧客データを活かした施策へ展開
CRMに蓄積された顧客データを、MA(マーケティングオートメーション)ツールと連携させることで、メール配信やキャンペーン管理などの施策に活用できます。
たとえば、CRM上の「見込み度」「業種」「商談履歴」をもとに配信リストを自動生成すれば、営業とマーケティングが同じデータを見ながらアプローチでき、重複接触や抜け漏れを防げます。
さらに、施策効果(開封・クリックなど)がCRMに反映されることで、営業は関心度の高い顧客を把握し、次の提案やフォローに活かすことができます。
「連携」を前提にしたCRM設計が、定着と成長を支える
これまで見てきたように、CRMを他のシステムと連携させることで、業務の効率化や情報共有、データ活用など、さまざまな効果を得ることができます。
しかし、その効果を一時的なものにせず、組織全体で持続的に活用していくには、「連携」を前提にしたCRM設計そのものが欠かせません。
CRMを業務の“ハブ”にする発想
これまでのCRMは「顧客情報を管理するツール」として扱われがちでした。
しかし、CRMの本来の役割は“顧客を中心に業務をつなぐ”情報基盤です。
各部門でバラバラに動いていた業務フローをCRMに集約し、情報の起点を一本化することで、組織全体が同じデータを共有。営業・サポート・会計など、あらゆる業務がCRMを通じて連動する「ハブ構造」が理想です。この構造によりCRMは「報告のためのシステム」から「仕事を進めるための仕組み」に変わります。
現場が使い続ける仕組みとしてのCRM設計
CRMが定着しない最大の理由は「現場の業務フローに合っていない」ことにあります。業務手順や入力項目が実態とずれていると、使い続けることが負担になります。
定着を促すには「業務プロセス」と「CRM設計」をセットで見直すことが重要です。
たとえば
- 現場の入力作業を最小化(自動登録・テンプレート化)
- 他システムとの連携で二重作業を排除
- データを見返す機会を設計(レポート・共有ダッシュボードなど)
現場の業務をしっかり理解し、実際の業務フローに沿った設計を行うことで、CRMが業務の中に定着しやすくなります。
CRMを選ぶときに押さえておきたいポイント
ここまで紹介してきたように、CRMを中心に業務やシステムをつなぐことで、情報共有の効率化や業務負担の軽減、データ活用の高度化など、多くの効果が期待できます。
では、「顧客を軸にした業務連携」を実現するには、どのようなCRMを選ぶと良いのでしょうか。ここで、CRMを選ぶときに意識しておきたいポイントを整理します。
- 顧客情報を中心に、営業・サポート・会計などのデータを一元管理できる
- 他システム(販売管理・MA・CTIなど)との連携が容易である
- 部門をまたいで同じ情報をリアルタイムに共有できる
- 現場の業務フローに合わせて柔軟に設計・拡張できる
- 蓄積したデータを分析し、判断や改善に活かせる構造を持っている
これらの条件を満たすCRMの一例として挙げられるのが、オープンソースを基盤とするF-RevoCRMです。自社の業務フローや既存システムとの連携を前提に設計でき、営業・サポート・販売管理・マーケティングなどの情報を一元的に扱う構造を備えています。
まとめ ― 「システムをつなぐ視点」
CRMは単体で導入しても、データが十分に活かされず、「入力のためのツール」にとどまりがちです。他システムと連携させることで、データの一元化や業務効率化、運用の定着が進み、組織全体での顧客対応力を高めることができます。
たとえば、F-RevoCRMのように、オープンソースを基盤として多用なシステム連携を柔軟にできるCRMは、こうした「連携を前提にした運用」を実現しやすい仕組みといえます。
CRMを業務の中心に据え、他システムとの関係を設計し直すことで、「使うCRM」から「使われるCRM」へと進化させることが可能になります。
まずは自社の業務フローを可視化し、どのシステムととどのデータをどうつなぐべきかを整理することが、CRMを本当に活かすための第一歩です。
![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)