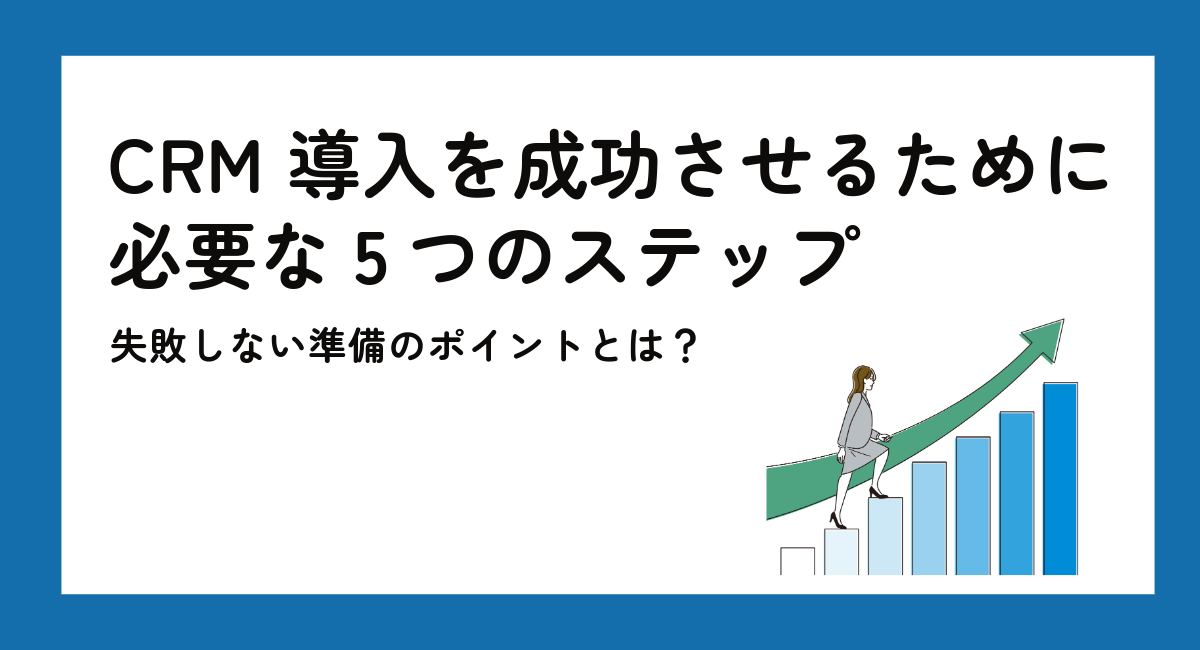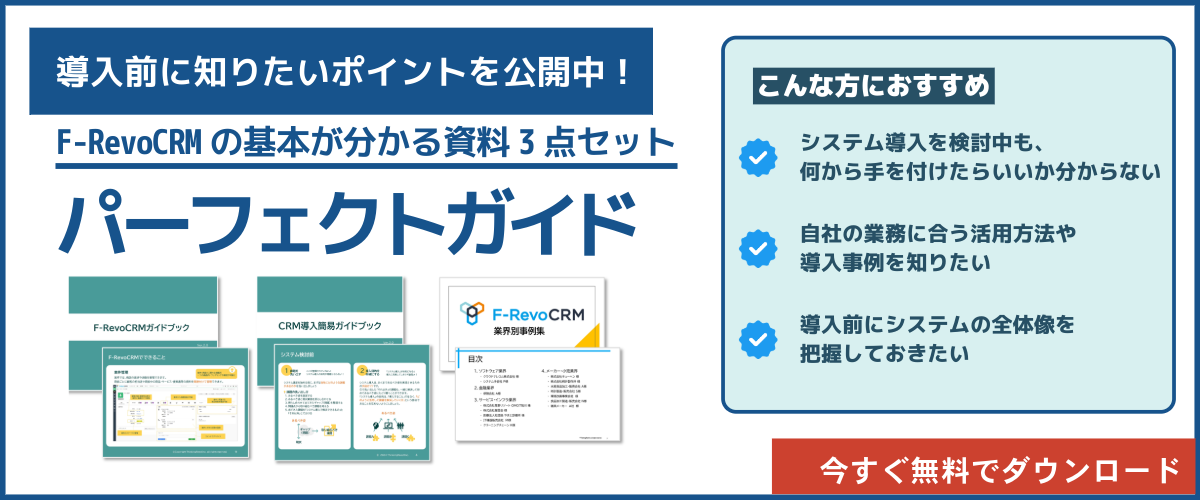「CRMを導入すれば、業務効率がすぐに上がる」——そんな期待を持ってスタートする企業は少なくありません。しかし、現実はそう甘くはないのがCRM導入の難しさです。単にシステムを導入するだけでは、本来得られるはずの効果を十分に引き出すことはできません。
本記事では、CRM導入を成功させるために必要な事前準備と、押さえるべき5つの重要ポイントについて、わかりやすくご紹介します。
関連記事:CRMとは?
自社の課題を洗い出す
導入効果を最大化するためには、現在の業務プロセスにどのような課題があるのか、どの業務を改善したいのかを明確にする必要があります。
課題をあいまいなまま進めてしまうと、システムは導入できたものの、結局使いこなせない——という結果になりかねません。
課題の洗い出しはどう進めるか?
課題整理の第一歩は、「現場の声を拾うこと」です。
営業、カスタマーサポート、マーケティングなど、顧客接点を持つ部門を中心に、日々どのような業務に負担や非効率を感じているかをヒアリングしましょう。
たとえば、次のような観点で質問していくと、実態が見えやすくなります。
- 顧客情報を探すのに時間がかかっていないか
- 見積書や契約書の作成に無駄な手作業が発生していないか
- 顧客とのやり取りが部門内で共有されているか
優先順位をつける
課題を洗い出した後は、すべてを一度に解決しようとするのではなく、優先順位をつけることが大切です。
ポイントは、「業績や顧客満足度への影響度」と「緊急性」の2軸で考えることです。
たとえば、営業活動に直結する「案件管理の属人化解消」は高い優先度になります。一方、「データ分析の自動化」は、当面の業務には支障がないなら、後回しにする選択もあり得ます。
優先順位が明確になれば、必要な機能要件もはっきりし、システム選定や導入プロジェクトの進行もスムーズになります。
「CRMを入れること」が目的になっていないか確認する
CRMはあくまで手段であり、ゴールではありません。
本来の目的は、業績向上、業務効率化、顧客満足度の向上などの課題を解決することにあります。
では、どうすれば「手段の目的化」を防ぐことができるのでしょうか。
まず、「なぜCRMなのか」を明確にする
CRM導入に着手する前に、必ず確認してほしいのが「私たちはなぜCRMを導入しようとしているのか?」という問いです。
この問いに対して、シンプルかつ具体的に答えられる状態をつくることが重要です。
たとえば、こんなふうに言語化できているでしょうか。
- 案件管理を見える化し、失注を減らすため
- 顧客対応履歴を部門間で共有し、サポート品質を統一するため
- 蓄積したデータをもとに、より精度の高い営業戦略を立てるため
もし、「なんとなく便利そうだから」「他社も入れているから」といった曖昧な理由しか出てこない場合は、一度立ち止まって目的を整理し直す必要があります。
目的が明確なら、選ぶべきCRMも自然に決まる
CRMは世の中に多種多様な製品が存在します。
営業支援を得意とするもの、マーケティング機能に強いもの、カスタマイズ性に優れるもの……選択肢は豊富ですが、だからこそ「何のために使うか」が決まっていないと、選定基準すらぶれてしまいます。
一方、目的が明確であれば、
- 「必要な機能」
- 「重視すべき操作性」
- 「導入後の運用イメージ」
がクリアになり、CRM選定から導入後の活用まで一貫性のあるプロジェクトが実現できます。
業務フローを整理して、使う場面をイメージする
次に取り組むべきステップが、「業務フローの整理」と「利用シーンの具体化」です。
これができていないと、導入後に「誰も使わないCRM」になってしまうリスクが高まります。
目的が明確なら、選ぶべきCRMも自然に決まる
CRMは単なるデータベースではありません。
実際の業務プロセスの中で、必要な情報を記録し、共有し、活用するための仕組みです。
そのため、現行業務がどのような流れで進んでいるのかを整理しておかなければ、どこでCRMを使うべきか、どんな情報が必要なのかわからず、システムが現場から浮いてしまうのです。
たとえば営業部門であれば、
- 新規リードを獲得したタイミングで案件登録
- 商談ステータスの更新
- 成約後の受注処理
といった、CRMを活用する「業務上のタッチポイント」を明確にしておく必要があります。
「誰が、いつ、何をするか」を具体的に描く
業務フロー整理の際には、単にプロセスを並べるだけでなく、「CRMで何をどう記録・活用するか」まで具体的に設計しましょう。
ポイントは、
- 誰が(営業担当、マネージャー、サポート担当など)
- いつ(新規案件発生時、商談進捗時、クレーム対応時など)
- 何を(顧客情報、商談内容、問い合わせ履歴など)
入力または参照するのか、イメージを持つことです。
さらに、「その情報が、誰のどんな仕事に役立つのか」まで見通しておくと、現場の利用意欲も高まりやすくなります。
たとえば、営業が登録した商談履歴を、マネージャーが進捗確認やコーチングに活用する。
サポート部門が過去のやり取りを参照して、迅速かつ的確に対応する——。
このような「使われる未来」を描けるかどうかが、導入後の定着率を大きく左右します。
顧客情報のダブりをなくしておく
CRM(顧客管理システム)を導入する際、忘れがちですが非常に重要な準備作業があります。
それが、「顧客情報の重複をなくして、データをきれいに整える」ことです。
顧客情報の重複は、なぜ問題なのか?
たとえば、同じ企業が
- 「株式会社○○」
- 「(株)○○」
- 「○○会社」
と表記違いで複数登録されていたらどうなるでしょうか。
営業担当ごとに管理されている顧客リストもバラバラ、商談履歴も分散してしまい、全体像を把握するのが困難になります。
さらに、二重アプローチによる顧客の不信感を招いたり、正確な売上分析やキャンペーン効果測定ができなくなったりと、ビジネス全体に悪影響を及ぼします。
CRMを「正しく」「効率的に」活用するためには、こうした重複データの問題を事前に解消しておく必要があります。
データ整理は、こう進める
CRM導入前のタイミングで、以下のような流れでデータ整理を進めるのがおすすめです。
- 既存の顧客データベースを一覧化する
まずは現在保持しているデータをすべてリストアップし、俯瞰して確認できる状態を作ります。
- 重複・類似データを洗い出す
表記ゆれや、明らかに同一と思われるデータを抽出します。
- 統合ルールを定め、整理する
「正式社名に統一する」「住所や電話番号も正確なものを優先する」など、統合基準を定め、データをまとめていきます。
- 整理後も継続的にメンテナンスできる体制を作る
一度きれいにしても、運用中にまた重複が発生するリスクがあります。定期的にメンテナンスするルールを設けましょう。
地味な作業ではありますが、ここを丁寧に進めることで、CRM導入後のスムーズな運用と高い活用効果を確実に引き出すことができます。
社内の「言葉」をそろえる
営業部では「得意先」、管理部では「顧客」——。
意味は同じでも、呼び方が違うだけで情報共有はグッと難しくなります。
CRMを使うなら、社内全体で「共通言語」を作ることが大切です。
「共通言語」が必要な理由
たとえば「リード」という言葉ひとつとっても、部署ごとに解釈が違うことはよくあります。
- マーケティング部門では、「資料請求をしてくれた見込み客」をリードと呼ぶ
- 営業部門では、「商談化が見込める顧客」だけをリードと呼ぶ
このようなズレを放置したままCRMを導入してしまうと、登録されたデータやレポート結果の解釈にズレが生じ、
「どれが本当の数字なのか分からない」「データが信用できない」といった混乱を招きます。
CRMは「顧客情報の一元管理と共有」が本来の目的ですが、そもそもの用語の認識がバラバラでは、共通基盤を築くことはできません。
どのように共通言語を作るか?
共通言語を整備するためには、次のようなステップが効果的です。
- 主要な用語を洗い出す
営業、マーケティング、サポートなど、CRMで扱う情報に関わる部門同士で、使用している用語をリストアップします。
- それぞれの部門での意味をヒアリングする
同じ言葉でもニュアンスや対象範囲が違う場合が多いので、実態を把握します。
- 社内で統一ルールを決める
たとえば「リード=初回接触した見込み客」「案件=商談化した顧客」など、明確に定義してドキュメント化します。
- 全社に共有し、定期的に見直す
共通言語は一度決めたら終わりではありません。組織の変化に合わせて更新していくことも大切です。
事前準備がCRM導入成功のカギ
CRM導入を成功させるカギは、システムそのものではありません。
ポイントは、「自社の課題を整理し、業務フローを見直し、使い方のルールを決めておく」ことにあります。
- 何のためにCRMを使うのか
- どの業務に、どの場面で使うのか
- 顧客情報をどう整理し、どのように運用するのか
- 社内で言葉の定義を統一できているか
これらを事前に整えておかないと、どんなに高機能なCRMを入れても、現場に定着せず形だけのツールになってしまいます。
CRM導入は「システムを買う」ことではなく、「業務のやり方を整え、組織としてデータを活かす力をつける」取り組みです。
まずは、現場の運用イメージをリアルに描きながら、一歩ずつ準備を進めていきましょう。
![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)