Interview-東大襖クラブ

60年の伝統と技術を引き継ぎ、襖の張替えを行う東大襖クラブでオープンソースCRMであるF-RevoCRMを導入。
その狙いと、導入後具体的に何が変わったかをお伝えする。
はたして、CRM導入の成果は…?
襖クラブの実態は零細企業そのもの。
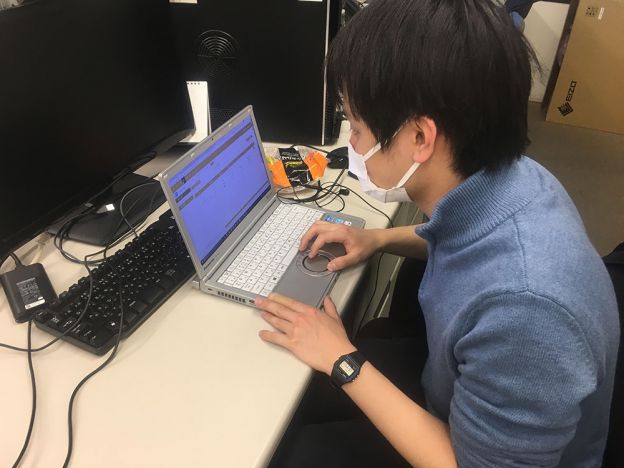
東大襖クラブは大学のサークルでありながら、その実態は零細企業そのものである。
彼らは、単に趣味で襖を張り替えている訳ではない。第2回でもお伝えしたとおり、襖の張替えの依頼が一般家庭や旅館などからきて、張替え作業を行い、お金を受け取るという事が基本的なサービスであるが、そのサービスを実施する為には、部員たちのスケジュールを調べてアサイン、襖紙の発注、見積書の作成、請求書の発行、部員への日当と、サークルへの納入、といった通常の企業活動と同様の「業務」がある。
しかも、テレビ取材などを受けると大量の依頼が入ってくる為、これらの「業務」は相当な負荷となってしまう。また「お金」が関わる以上、大学のサークルだからといっていい加減な事はできない。紙やExcelを使って行っていた「業務」の負荷を下げ、且つミスも減らす。これらがF-RevoCRMを導入した狙いだ。
F-RevoCRMを導入して何がどう変わったのか
では、F-RevoCRMを導入して具体的に何がどう変わったのか?その内容を業務プロセスに従って説明したい。
- 襖の張り替えをメールや電話で受注
顧客情報と依頼内容を登録しておけば情報が残る様になった。
- 部員たちのスケジュールを調べ、日程と担当を割り振る
予定表の張替え一覧を見て、日程を押さえる
お客様・案件情報の登録
<ポイント>
- 担当の決定が短時間で可能になった。
- Excelの場合は出先で作業できなかったが、メールを送れば情報が登録できるため出先から登録が可能になった。
- 最寄り駅検索をカスタマイズで追加したため、近隣の部員のアサインが可能になった。
- 担当が襖紙の見本帳を持って訪問し、見積書を発行
その場でシステムに登録されるため、手書きの紙や記憶に頼る必要がなくなった。
見積書印刷が不要であれば、その場でメールも送信できるようになった。
<ポイント>
- 見積書の紛失などのリスクがなくなった。
- 見積書の発行にはシステム登録が必要なため、必ず正しい情報がシステム上に存在するようになった。よって、うろ覚えで紙の発注をせずに、見積ベースで紙の発注をするため、誤発注がなくなった。
- 複数人数の仕事の場合は、担当が作業要員を集める
予定表を見れば、案件の日付が反映されていて、予定表上で空いている部員をアサインすれば良くなった。
- 作業当日に材料費・作業費・交通費を受け取り、請求書・領収書を発行
見積から請求書・領収書がワンクリックで作成可能になった。
<ポイント>
- PDF出力をカスタマイズして角印が押された状態のため、メール送信やすぐに印刷して提出が可能になった。
- 受け取った代金から一定割合をサークルに納入
納金モジュールにデータが自動的に集約され、個別の複雑な計算が一切なくなった。
<ポイント>
- 「請求書から手動で割合計算をして、時には複雑な会計処理が必要」「一人年間20〜30件の溜まった代金を一括で処理をしていたため、計算ミスが多発」また、「会計側でのチェックが大きな負担」といった問題が解決した。
- 情報が集約されたことにより未納総額の管理も可能に。
如何であろうか、紙やExcelで行っていた「業務」をシステム化して情報を集約する事でこれだけの成果をあげる事ができたとの事だ。
編集後記
3回にわたりお伝えしてきた、「東大襖クラブ×F-RevoCRM」如何でしたでしょうか。
「東大襖クラブ」はキラキラしていない。とても真剣に取り組んでいるが、体育会系とも違う。その中身は伝統的な零細企業とまさに同じだ。
授業では最新のITを学びながら、零細企業を経営し、自ら職人として腕も磨き、その中で、伝統やネームバリューに甘える事なく、課題を見つけ、課題を解決していく。これほどの「学びの場」はそうはないだろう。
また、彼らの考え方がとてもフラットな点も新鮮に思えた。企業がシステムを導入する場合は「あの企業も使っているから…」「有名なシステムだから…」何かと前置きをつけたがるのに比べ、自分達が感じた課題に対してストレートに、最短距離で解決できる道具を探し、やり方を探し、すぐに実行している。
「東大生は頭でっかちで実社会での能力は別。遊びとか一杯経験していた方が…」たまに聞く言葉だが、彼らに関しては、そんな批評は微塵も感じない。
近年、日本の労働生産性の低さが指摘されているが、確かに「うちは古い会社だから」「うちは小さい会社だから」「システム導入しても使いこなせない」という言葉を今まで何度も聞いてきた。大手であっても、古い社員や経営陣が若い社員に、これがうちのやり方だから、とExcelと紙での業務を押し付けて残業させる。そんな光景も何度か見てきた。
彼らがもしそんな会社に入社したら、これ程の無駄はないだろう。
優秀な人材がどんどんと海外、外資に流れていってしまうのも仕方がないとも思える。
その様な人材を生み出す素晴らしい「場」である、伝統的零細企業「東大襖クラブ」の発展と永続を心より願わずにはいられない。そして、今後の彼らの活躍を期待したい。
できれば、日本で…と、思うのは安い情緒論だろうか。


![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)